5年生の我が子について。
公立中高一貫校の中学受検に向けて、本日も塾へ行ってきました。
ここ数ヶ月は、天候や学校行事以外で休むこともなく、順調に通塾しております。
そして、先月に受けた適性検査対策模試の成績表が、本日返却されました。
結果は、反省点だらけです。
この記事は、今回返却されたテストの反省点から考える、一般の学力テストと適性検査対策模試についての、出題形式や対策についてまとめています。
この記事で書かれている、反省点やもっとこうしておけば良かったなどの改善点など、皆さんが、実践出来るような情報がありましたら、どんどん活用してくださいね。
気になるポイントは、各目次からご確認ください。
適性検査と一般試験の出題形式
今回返却された模試は、2回目の適性検査対策模試となります。
娘も含め、塾生の皆さんにとっては厳しい結果となったようでした。
そして先生からは、以下のようなクラスルームへのメッセージが送られてきました。
適性検査対策模試は、通常行われる学力テストとは異なる出題形式のため、難しく感じることがあります。
ですが、学校や塾、ふだんの生活から学んだことをもとに作成されていますので、
「難しそう」という気持ちをふりほどいて、問題に、まっすぐ、素直に向き合ってもらいたいと思います。
解く楽しみを体感できますよう、日常の授業や宿題、出来事に丁寧に取り組み、次回に向けての準備も進めていきましょう。
温かいお言葉です。
先生のおっしゃる通り、適性検査は通常行われる学力テストとは異なります。
通常の試験については計算をすることや文章問題を解く中で、難問なども出題されることが一般です。
そのため、基礎学力を徹底したうえで、もっと深いところまで掘り下げた学習を行う必要があります。
適性検査については、通常の試験と同じく基礎学力を徹底したうえで、応用力を養う必要があり、自身の経験をもとに解答する問題が出題されます。
また、文章の中に入る適切な言葉を、選択形式ではなく自分の言葉で書き込むことや、自身の思いを文章を使い、いかに表現できるかを問われる問題形式が出題されることとなります。
適性検査1の漢字の強化
公立中高一貫校の入試でおこなわれる適性検査1は、文系の国語となります。
適性検査の文系については、読解力、文章力、表現力、に尽きます。
そして、漢字の読み書きは出題されないことがあるようです。
しかし、公立中高一貫校の入試を経験した先輩方は、
「もっと漢字の勉強をしておけば良かった」
皆さん口をそろえて言っています。
では、漢字の読み書きの問題が出題されないのに、なぜ漢字の勉強をしておけば良かったのか。
それは解答する際に、習った漢字は使わないと減点されるからです。
文系の文章問題について
適性検査1の文系では、試験内容はほとんどが文章問題で構成されていました。
文章問題の中に穴埋め問題があり、適切な言葉を記入するという形式となっています。
こちらの穴埋め問題については、選択問題もありますが、ほとんどが自身で適切な文言を記入する形式となっていました。
例えば、下線1は「3文字」など、文字数が決められている中で、自身の言葉を適切に記入するということです。
類似している言葉を記入しても、それだけでは不正解となります。
また、伝わりにくい文章についても減点対象となります。
最終問題の作文について
最終問題の、150以上から200文字以内で記入する問題については、5年生の模試の場合は配点が34点です。(※5年生の適性検査対策模試の作文配点は34点ですが、6年生の模試と入試の作文配点は13点となります 2023年時点)
しかし150文字以下の文章は、失格なので配点は0点となります。
そして解答する際には、2段落構成で書くことや、鍵カッコは改行しないなど複数の指示があるので、指示通りの構成で文章を作成する必要があります。
こちらについても、構成を間違えた際には減点、又は、配点が0点になることもあります。
5年生の適性検査対策模試では、字数、段落、独創性、段落、倫理的表現、を合わせての評価から、最大34点とされていました。
以上のことから最終問題の作文については、ただ150文字以上の文章を作成するたけではなく、文章の質も重要となってきます。
娘は、前回おこなわれた第一回目の適性検査対策模試では、時間が足りなく最終問題までたどり着けなかったため、配点が0点でした。
娘のクラスの塾生さんたちも、全員が最終問題までたどり着けなかったそうです。
つまり、他の問題が全て正解であっても、66点ということになります。
適性検査については、皆が初めての模試なので、仕方ないかも知れません。
娘については、前回の教訓を活かして今回は、最終問題の作文を優先的に解いたそうです。
そして、34点中、32点は獲得してきました。
2点の減点については、言葉の表現と独創性について減点されていました。
娘の作成した、作文の表現について、
「あまい物を食べたりして休けいしています。」
こちらは、「食べたりして」ではなく、「食べて」が正となります。

独創性については、
「自分1人だけではなく、他の人と影響しあってリードしながら行動する意欲を伝えられるとより良い」
と指摘がありました。
このように作文は、文字数以外にも、文章の構成や適切な漢字を使う事など、文章の質についても、気をつける必要があるようです。
その他、試験においては時間配分も大きな課題と感じています。
適性検査2は理系という名の文系
適性検査2について。
こちらは、理系の問題が出題されています。
しかし、目次のタイトル通りですが、理系とはいっても文系のような文章で構成されている形式の問題が出題されていました。
適性検査1と同様に、文章の穴埋めがあり、選択問題もありますが自分の言葉で答える形式です。
そして文章の穴埋めについては、実際に対話しているような会話文を問題としているため、日常生活から得た知識や、深く物事を読み解くスキルが重要となることが分かります。
今回の模試では、理科でおこなう対照実験やオセロのようなゲームについての勝敗を読み解く問題が出題されていました。
一般的に、将棋や囲碁は数学と通ずるといわれていることから、今回の適性検査2のゲームの読み解きについても、典型的な理系の問題内容と感じられます。
正しい読解が必要な理由
対照実験については、種子の発芽に関する実験内容でした。
こちらの実験は、「真っ暗なあたたかい部屋と冷蔵庫」でおこなわれる対照実験となります。
そして種子の発芽の条件として、空気がひつようであるかを調べる実験について、下線は正しい、正しくないかを問われる問題が出題されました。
その他、その理由も書きなさいとされていました。
会話文:種子イと種子ウを比べるのではなく、種子イと種子クを比べてもいいと思います。
実験の条件
- 真っ暗なあたたかい部屋と冷蔵庫
- 脱脂綿の中と水の中
娘の解答
これは、不正解です。
正しい解答は、
娘も正しい解答については、理解をしていたので、書くこともできたそうです。
ではなぜ発芽についての明確な解答をしなかったのか。
それは、学校の先生から理科の授業の際に、このように教えてもらったそうです。
学校の先生『対照実験に関しては、「対照実験をするときは、変える条件は1つだけだから。」
と答えれば正解です。』
つまり、学校の先生が話す言葉を、そのまま捉えてしまったようです。
娘は、対照実験の定義を、発芽の条件と読解したようでした。
学校の先生については、クラスの皆に分かりやすく伝えるために、ざっくりと話しただけです。
ある意味、5年生の現時点で、この勘違いに気が付けたことはラッキーかも知れません。
反省点と今後について
子供は多くを吸収します。
正しいこと間違っていること、全てを全力で吸収しています。
今回のテストから学んだ事として、物事を正しく捉える力は、とても大切と感じました。
そして状況によって、臨機応変にに対応できる力は、受検に必須な力と感じています。
娘については、今後も失敗を教訓として、頑張ってもらいたいと思います。
そしてこの記事が、皆さんの学習のヒントになれたら嬉しく思います。
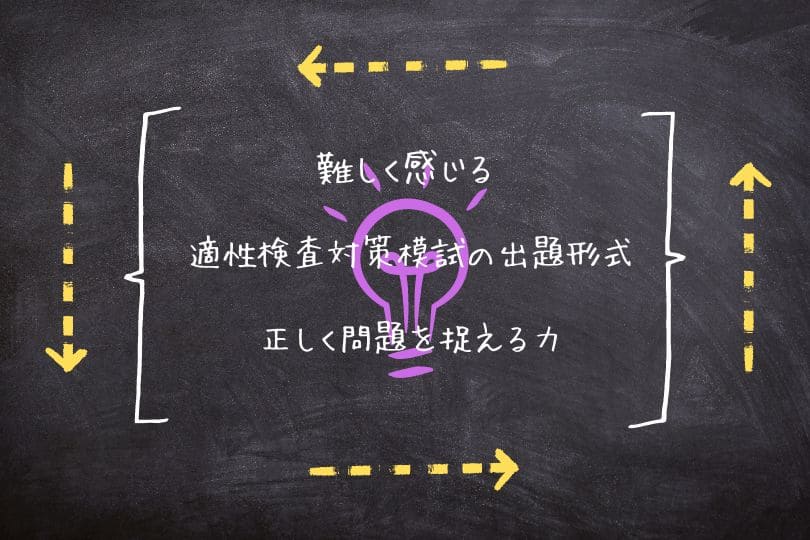


コメント