4月から6年生になった娘。
5年生の春から公立中高一貫校の受検を目指しています。
そして先日、6年生になって最初の適性検査対策模試を受けてきましたが、手応えは最悪のようで本人もショックを受けていました。
この記事は、娘が失敗した大きな原因と反省点、その他気をつけたい事柄や、適性検査の性質を知り、合格を掴むための対策についてまとめています。
この部分を気をつければ次回に役立つなど、娘と話し合いをした内容なので、皆さんも参考になることがありましたら、是非実践をしてみてくださいね。
点数取得の計画が裏目に
娘としては適性検査対策模試を受けるにあたり、今回は点数を取るための計画があったようです。
それは今年度から6年生ということで、適性検査対策模試の点数配分が5年生の頃と変わるということから、考えた計画のようです。
5年生の適性検査1の文系は、最終問題の作文配点が34点でした。
そのため今までは、34点は確実に落としたくないので、最後の作文問題から解くことを絶対としていたようです。
しかし6年生からは最後の作文問題は配点が13点となります。
最終問題の点数配分が少なくなる分、問題数も増え難易度が上がると耳にした娘は、最初の問題からコツコツと解く方法をおこなったようでした。
これが点数を大きく落とす原因です。
実際に模試を受けてみると、6年生の4月におこなわれる適性検査対策模試については、出題範囲が5年生の総合なので、文系の最終問題も配点が34点でした。
そして娘は最初からじっくり解いていたことから、最終問題の作文までたどり着けずに34点をまるまる落としてしまいました。
読み解く力があり、最初から解いても時間内に終わる実力があるなら良いのですが、うちの娘については解ける問題を確実に落とさないことが1番点数を取れる方法となります。
解ける問題を見極め、時間のかかりそうな記述問題は、時間が余った状態でじっくりと解くことが最善の策なのです。
今回の娘は、最初からコツコツと解いて記述問題に時間をかけてしまった結果、最終問題の作文まで辿り着くことができずに、時間をかけた記述問題も間違えてしまったという最悪な状況となりました。
模試を解くコツとしては、時間配分と合わせてどこの問題から解き始めるかの見極めが大切ということのようです。
「解ける問題や配点の高い問題は確実に落とさない」
こちらは、実力がついても大切と感じました。
もったいないミスをなくす
そしてもったいないミスとしては、漢字の間違いです。
適性検査2の理系では、並列と直列について出題されていて、並列を平列と漢字を間違えてしまいました。
授業では、並列はひらがなで「へい列」と習ったようです。
習っていない漢字を間違えるよりは、ひらがなで書いた方が良いということで、漢字の間違えは減点ではなく不正解となります。
問題を解くスピードを上げる対策
適性検査1の文系と、適性検査2の理系。
娘は、時間をかければ解けるけど、時間が足りなくて最後まで解けないと言っていました。
「なぜ解くのに時間がかかるのか?」
こちらについては、適性検査のような出題形式の問題に触れる機会が少ないため慣れていないからとのこと。
つまり、演習量が足りないのです。
通常おこなわれる塾内の学力テストや、年に数回実施される全体の学力テストのような強化型の出題形式には慣れていますが、適性検査のような出題形式は解く回数が少ないことも、時間が足りない要因の一つと感じています。
実際今までも、強化型学力テストの偏差値と適性検査対策模試の偏差値は、かなりの違いがありました。
今後の受検対策については、娘と話し合った結果、先日の模試で貰った画像の冊子。
とりあえずこちらを進めてみることにしました。
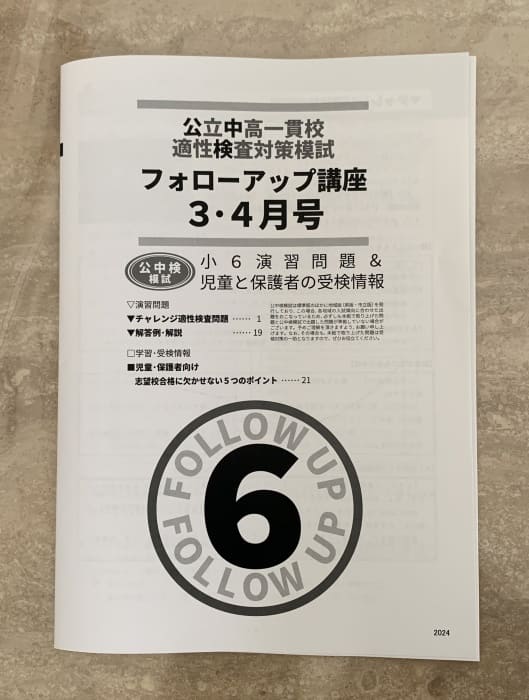
こちらの冊子(公立中高一貫校 適性検査対策模試 フォローアップ講座)は、適性検査対策模試を受けると付属して貰えます。
そして適性検査の例題や志望校合格に欠かせないポイントなど、受検に役立つ耳よりな情報が書かれていました。
今週末からゴールデンウィークに入るので、学校や塾が休みの間に、この冊子をじっくりと学習したいと娘は言っています。
適性検査で合格を掴むために
今回貰った冊子(公立中高一貫校 適性検査対策模試 フォローアップ講座)に、
「志望校合格に欠かせない5つのポイント」
がありました。
この冊子を持っている方は、21ページと22ページに適性検査のポイントが記載されているので、ぜひ読んでみてください。
合格をするための対策として、とても納得できる内容が書かれていました。
また、公立中高一貫校の適性検査は難しいので、
「学校で習う教科書の範囲以外が出題されてるのではないか」
と思ってしまうことがありますが、そうではないことも分かりました。
基本的に適性検査で出題される問題は、小学校の教科書範囲をもとに出題されているそうです。
ここからは持論となりますが、学校での学びや教科書の内容など、基本的な基礎がしっかりと理解できていることが大切であり、基礎力は適性検査の入口のようなものと思われます。
しかし入口だけでは適性検査で点数を取得できないということで、学校の教科書以外の学習が必要であり、「難しいので特別な学習を取り入れる必要があるのではないか」と、世間では言われているように感じます。(過去の私もそうでした)
うちの娘を例えとすると、娘は学校で習う教科書の基本的理解はできているようです。
そのため学校のテストでは、100点しか取りません。
また委員長なども積極的におこない生活面も含め、通知表では全教科と、右側にある全ての項目が、オール◎です。
しかし適性検査対策模試では、いつもひどい点数で6年生最初の模試は、おそらくE判定になると思います。
小学校の教科書範囲をもとに出題されているなら、
【全教科、全ての項目がオール◎でなぜ解けないのか。やはり適性検査はそれ以上の学習や学力が必要ではないのか。】
これについては、半分正解で半分は違うと思います。
つまり娘については先程述べた、「入口」部分、基礎の入口はできているけど、その先の応用的に考える力が足りないと言えるのだと思います。
応用問題というと学校以外の学習と感じてしまいますが、適性検査に出題される応用は、私立受験のように高度な難問ではなく、生活の身近な事柄が多くあります。
そして学校でおこなわれる授業の全てには、適性検査の問題を解くヒントが詰め込まれていることも分かります。
学校で育てている植物や、家庭科の授業から得る食育、児童会でおこなわれるリサイクルやボランティア活動。
植物については理科の理系、リサイクルやボランティア活動については、社会科として文系の要素があり、適性検査で出題されそうな事柄となります。
このような事柄を適性検査では、図で展開されたものを割合で求めることや、記述問題として出題される傾向にあるように思われます。
以上のことから、日常生活の隅々までアンテナを張り、考える力を養うなどが必要とされることは、納得ができます。
うちの娘のように、強化型の偏差値と適性検査の偏差値に大きな開きがあるのは、学習面の基礎と応用はできていても、生活面やあらゆる事柄に対する応用力が足りないということが分かります。
前項目で書いた娘の言い分は、「時間をかければ解ける」ですが、時間をかけずに解く力を身につけるには、応用力とプラスアルファ演習量が必要となります。。
過去記事でも公開していますが、娘の通う塾では、
常に思考を柔軟にすること
日常の授業や宿題、出来事に丁寧に取り組むこと
解く楽しみを体感すること
このように先生がおっしゃっていました。
適性検査のポイントは、学校で習う基礎学力とプラスアルファで上記のような応用力が大切で、小学校生活の中で育まれることが必要不可欠なのだと感じました。
以上が、模試の反省点から学んだ、適性検査の性質を知り合格を掴むための対策となります。
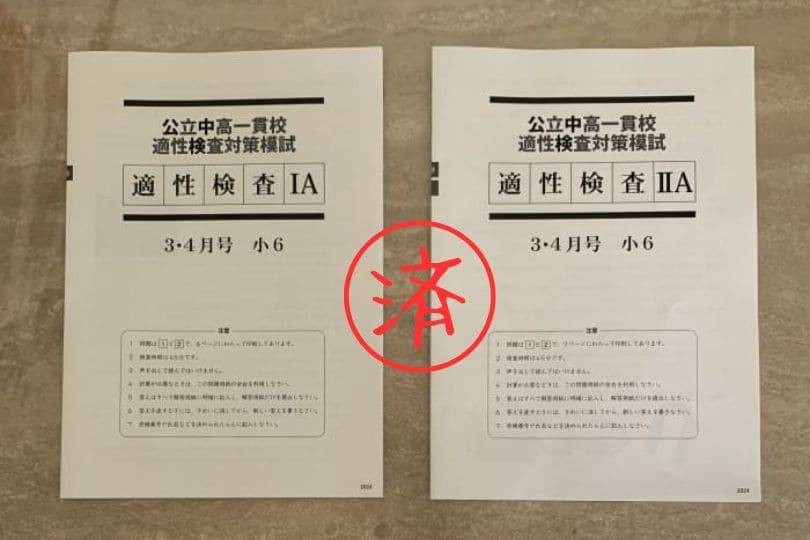
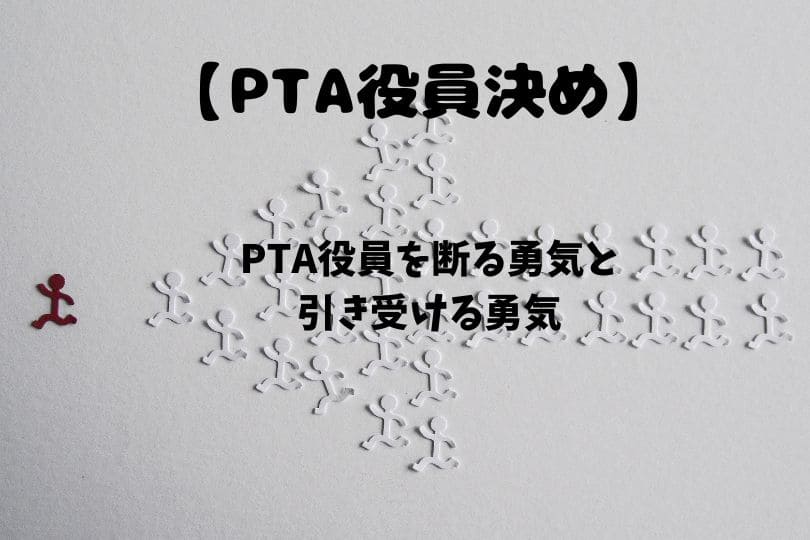

コメント